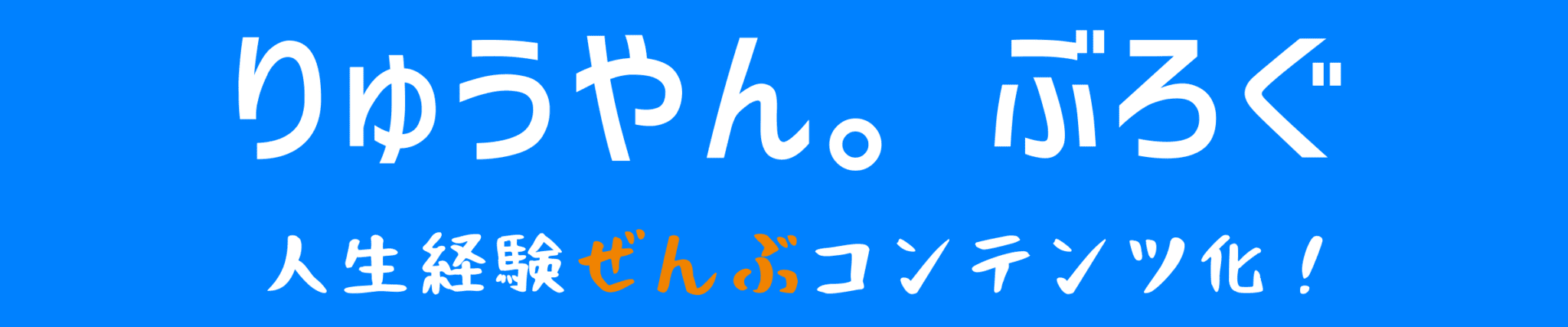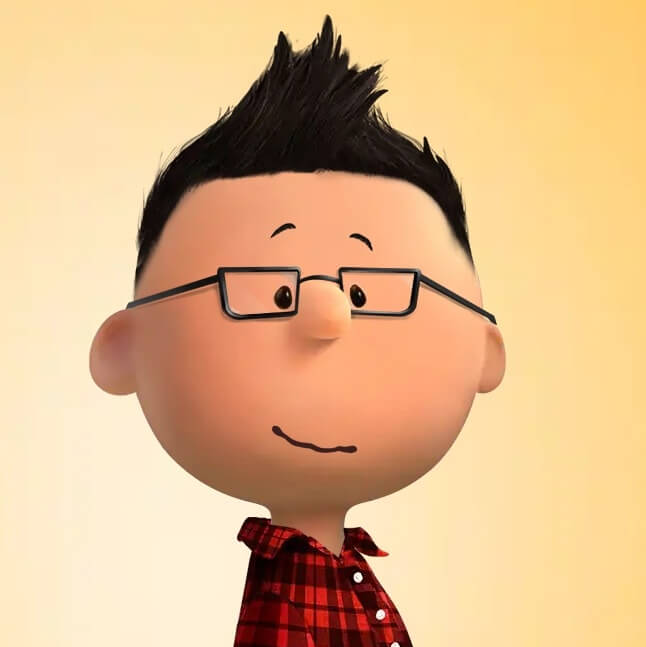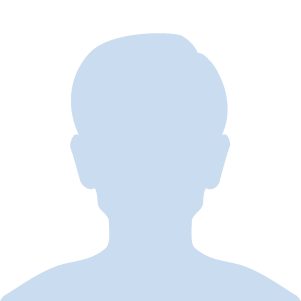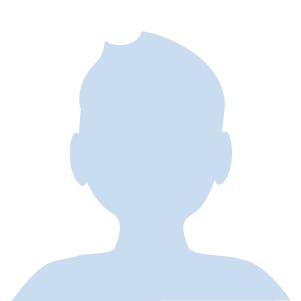こんにちは、りゅうやん。です!
以前、Twitterにてこんな投稿がありました。
有給取得時に理由を書かないとダメな会社にいる場合は、下記のように記入することをおすすめします。一発申請OKとなることうけあいです。
「労基法で定められた従業員の権利を行使するため」
— 米村歩@日本一残業の少ないIT企業社長 (@yonemura2006) July 23, 2019
これを見たときに、
と、ちょっぴり後悔しました。
なぜなら、前にいたITの会社では、有給申請の理由で「私用のため」が使えず、なぜ休むのかを根掘り葉掘りと聞かれたのでした。
そのときのことを、今回は振り返ってみたいと思います。
IT業界での有給申請
IT業界での「客先常駐」といった、自分が勤めている会社に出勤して働くのではなく、別の会社で働くかたちとなってます。

なので、有給をとるには客先(派遣先)と自社(派遣元)の両方に申請し、また両方から承認をもらわないといけないのです。
なんだかめんどくさいですよね?
でも、ぼくの有給申請でトラブルが起きたのは、
- 客先にいるとき
- 客先ではなく自社にいるとき
の2パターンがありました。
客先での有給申請でトラブル
客先常駐しているときは、常駐先だけでなく自社にも対して二重で申請して報告しなければなりません。
ただ、客先での担当者(上司)で承認を得られているならば、自社への報告は勤怠のときでいいみたいな決まりがありました。
ぼくが客先で有給をとろうとした現場に入ったのは、ちょうど8月だったので、常駐先では夏休みやお盆休みということもあり、派遣先の会社には人があまりいない状況でした。
ぼくは現場に入りたてなので、入っていきなりお盆休みをとるなんてことはできませんでした。
夏の暑い時期に休みをとれないのはしんどかったですが、それでも休みを申請できる出来事がありました。
それは、現場に入った年の11月に自社で社員旅行が企画されており、これに合わせて休みをとろうと思いました。
これを常駐先の上司に伝えたろころ、
と言ってもらうことができました。
同じ現場の先輩も、ぼくと同じように社員旅行に合わせて休みをとると言っていたので、先輩からの承認もOKでした。
しかし
自社のほうでは、これを良しとしなかったのです。
社員旅行の日程は、11月の上旬にある連休を使っていたので、平日の営業日にはかからないようになってました。
そこで、ぼくと先輩が出した有給は、その連休の前後に休みを入れるようなかたちで申請したのです。
ところが、
自社の上層部からはこれが気に食わなかったのか、対面や電話で怒られるハメに。。。
その理由が、
- 他の社員は、旅行の次の日でもふつうに出勤して働くのに、なんで休むんだ?
- そんなに休みたいなら、社員旅行に行かなきゃいいだろ!
- 有給を取るのは権利だが、もうアルバイトではなく社会人なんだから、そこはちゃんと考えてくれよ。
とのこと。
さらに、今後同じことが2度とないよう、自社の役員や営業部に向けた謝罪メールを作成することに!
ぼくは泣きながら謝罪メールを書き、有給申請を撤回して出勤しました。
客先の上司だけでなく、同じ現場にいる自社の先輩にもお休みの承認をもらっていたのに、自社から受けるこの仕打ちは、ホントにひどいものでした。
また、入社1年めからすごいスパルタだなとも思いましたね。。。
自社での有給申請でトラブル
IT業界では客先常駐での仕事が基本となりますが、常駐先がないときは自社で待機している状態になります。
ぼくも客先の業務で体調を崩し休職していた時期もありましたが、復職した数日後に平日でどうしてもはずせない予定がありました。
この日に休むことを、復職した直後で申し訳ないとしたうえで有給をとりたいと自社の上司に伝えました。
すると、
もう絶句しましたよ。
「私用のため」が理由にならないなんて。。。
「私用のため」がダメだったので、このときの理由は「病院に行くため」とウソをつきました。
でも、ウソをついたからといって、会社に対して申し訳ないとか罪悪感はありませんでした。
だって、有給をとってまで休みたい理由とは、
ハローワークにて労働相談をする予約をとっていたから
あと、ついでに労働基準監督署にも行ってきましたがね。。。
まとめ
有給をとるのは、労働者の権利なのだから変に忖度する必要がないのに、
- 持病の治療で会社に迷惑をかけているとか、
- 新入社員だから、あまり大きいことか言えないとか、
- 当時はこの会社で長く働き続けたいと思っていたから、上司に嫌われたくないと思われたくないから、(カノジョかよ!)
いろんな理由によって、気を遣いながら有給の申請をしてました。
最終的には(個人的に)有給を100%消化できたので、そのあたりは良かったのかもしれません。
でも、手続きにおいてさまざまな壁や問題があったので、そのあたりの調整が大変だったことは言うまでもありません。
これはIT業界独特なのかな?と言われたら、そうなのかもしれませんね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
ではでは(^_^)v